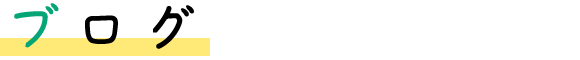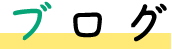会長ブログ
視線を外に向けよ

この世界のあらゆる要素は、互いに関連し、すべてが一対多の関係で繋がりあっている。
つまり世界にも、身体にも本来、部分はない。
部分と呼び、部分として切り出せるものもない。
世界のあらゆる因子は、互いに他を律し、あるいは相補している。
(福岡伸一「動的平衡3」)
万博も会期末が近づき、毎日たくさんの人が押し掛けています。
私も一度だけ、息子夫婦に連れられて(私には予約する能力がないので)、行ってきました。
この時、息子夫婦にひとつだけお願いしたのは、生物学者の福岡伸一さんがプロデュースした「いのち動的平衡館」の予約でした。
お蔭で念願が叶ったわけですが、実際の展示も福岡伸一の生命哲学がよく表現されたもので、それだけで行った甲斐がありました。
冒頭に掲げた福岡伸一さんの文章にあるように、宇宙に存在するもので、独立して存在しているものは、何ひとつとしてないのです。
あらゆるものが、関係し合い、互いに支え合って、はじめて存在しえるのです。
もちろん人間もその例外ではありません。
最近は「個」というものが、ずいぶん強調されていますが、この福岡さんの観点から「個」を理解しようとすれば、視線を外に向けて、他者との関係の中で「個」を見なければならないということになります。
視線を外に向けて、はじめて自分というものを理解できるのです。
私たちは不本意な困難に直面した時、その困難が自分にとって、どんな意味があるのかと問うてしまいがちです。
そして、その理不尽や不条理を怒ったり嘆いたり、果てはそれから逃げようとする。
しかし、それで逃げおおせるものではないし、却って理不尽や不条理は形を変え、そして大きくなってどこまでも追いかけてきます。
まして解決に至ることなどありません。
「自分にとって」と自分の内側に答えを求めても、そこに答は見つからないのです。
そんな時には、内を向いていた視線を外に向けてみる。
そうすると、その理不尽や不条理が自分だけに起きているものではなく、多くの人が同じ苦労を味わっていること、そして過去にもすでに幾多の人々がその苦悩を背負ってきたことが見えてくるのです。
そこに思いが到った時、はじめて自分に起きた困難に向き合えるようになるのです。
盲ろう者であった福島智さんは、視力を失ったのに加えて聴力も失い、他者とコミュニケーションが断たれたとき、こんな人生に何の意味があるのかと苦悩しました。
そして、自殺まで考えられたそうです。
その苦悩から福島さんを救ったのは、「宇宙が私の視力と聴力を奪ったのなら、宇宙は何らかの役割を私に与えているはずだ」との思いでした。
そして、その役割を考え抜いた結果、自分と同じ障害を持つ人のために役立とうと決意されて、障碍者福祉の研究の道に進まれ、東大の教授にまでなられたのです。
「役割」という言葉は、他者との関係性を意識するからこそ出てくる言葉であり、視線が外を向いてはじめて出てくるものです。
もし福島さんの視線が外を向かなければ、生涯世を拗ねて人を困らせる存在になっていたかもしれません。
そうならなかったのは、視線が外を向いて、自分の役割に気が付いたからです。
そこに至るまでの福島さんの苦悩はたいへんなものでしたが「全体の中での自分の役割」こそが、福島さんの人生を意味付け、苦難を乗り越えさせる原動力になったのです。
福島さんが、視線を転換するキッカケとなったのは、ヴィクトール・フランクルがアウシュビッツの体験をもとに書いた「意味への意志」の中にある次の方程式です。
絶望=苦悩−意味
意味を見出せない苦悩は絶望になる。
しかし、見出した意味が苦悩より大きければ絶望には至らないということです。
絶望の反対は希望ですから、この方程式は次のように書くこともできます。
希望=意味−苦悩
大きな意味を感じていれば、多少の苦悩があっても、それは希望となるということです。
「当社の目指す姿」にある「お客様の夢に寄り添い、笑顔とワクワクが止まらない会社」の「笑顔とワクワク」の実現は、「お客様の夢に寄り添う」ことの意味をどれだけ感じることができるかに懸かっていると言えるのです。
そして、それは視線を自分の内ではなく、自分の外に向けることから始まるのです。
私だけの人生などないのです。
周りの人や物によって生かされているのが、私の人生だということを深く考えたいものです。