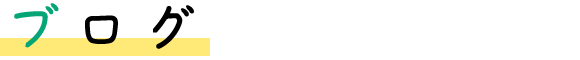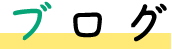会長ブログ
対話について
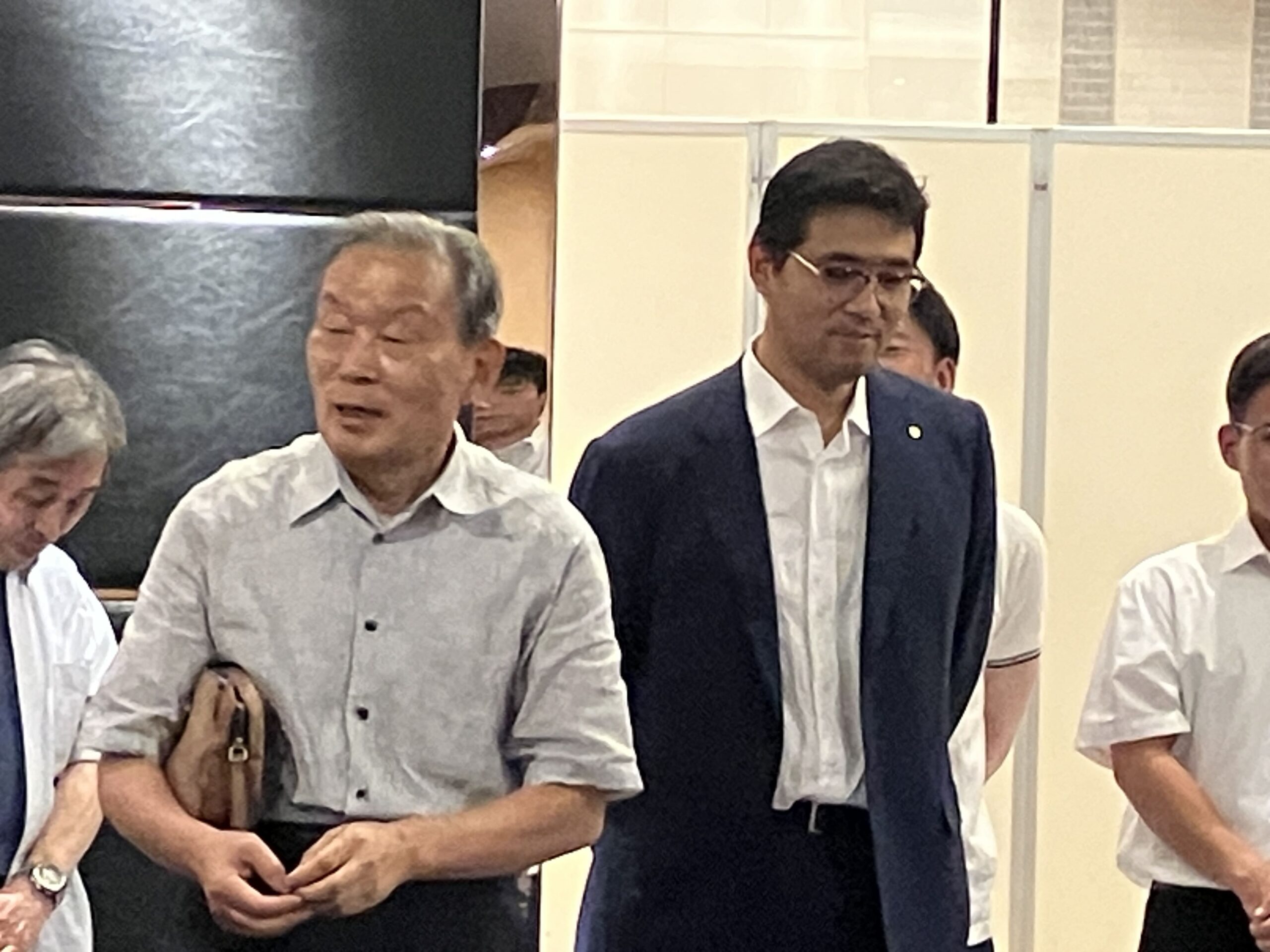
ただ残ったものは、海の底の音のようないく種もの耳鳴りだけだった。
そしてもっとも私を苦しめたのは、人と話せなくなったということだ。
私は孤独だった。
日記を書き、読書に没頭し、なんとかして気を紛らわそうとした。
でもその結果は寂しさを募らせるだけだった。
「私」という人間がこの世界に存在しているのだという自覚が、失われていくように思われた。
限定のない真空の中で、私は半ば死にかけている自分の精神を感じ、いいしれぬ恐怖感に襲われたものだった。
(福島智「ぼくの命は言葉とともにある」)
東大教授を務める福島智さんは、九歳で視力を失い、十八歳で聴力を失います。
冒頭の文章は聴力を失って間もなくの時期に、福島さんが書いた手記にある文章です。
視覚も聴覚も失うという苦悩の只中で、福島さんを最も苦しめたのは、人と話せなくなったということでした。
そのことによって、「私」という存在そのものが疑わしくなっていったのです。
何をしても紛らわすことのできない孤独感は、私たちのように当り前に話せる人間には、想像もつかないものです。
私たちは「私」というものは確固としてあると思って暮らしていますが、福島さんのこの文章から読み取れるのは、他者とのコミュニケーションが失われると「私」という存在の自覚さえ失われていくということです。
「私」はただ孤立して独自に存在し得るものではなく、他者との関係性の中で初めて「私」として自覚できるものだということです。
このことは、他者との対話というものが、いかに「私」を自覚する上で重要なものかということを示唆しています。
福島さんは、気配によって大勢の人の存在を察することができても、対話がなければ孤独は癒されなかったと言われています。
そう言えば、梅田などのひどい雑踏の中で、自分と無関係な人たちに囲まれた時、かえって孤独を感じた経験はないでしょうか。
物理的に沢山の人に囲まれていても孤独から救われることはありません。
人間的につながりのある人がいるかどうかが大事なのです。
孤独に陥らないためには、人間関係こそが必要であり、その人間関係をつくるためには、対話は必須なものなのです。
職場にあっても、同じことです。
仕事の指示だけしかない職場、同僚が自分の仕事の目的を果たすための道具に過ぎない人間関係であれば、それは梅田の雑踏に似ています。
そこに僅かでもいいから対話と言えるものがあるかどうかが大事なことだと思います。
当社では、元々社員が集まる機会が多いのですが、最近1ON1だとか、ファミリーコンパなど、益々対話の機会が増えてきました。
そこで単なる世間話や愚痴話に流されるのではなく、少しでも心の琴線に触れる会話がなされるようであれば、相互理解が深まり、益々本当の助け合いのある会社になっていくだろうと思います。
ぜひ、増えた機会を有効に使ってもらえればと思います。
人の幸福について、こうだと論じるのは大変難しいことです。
しかし、これだけは言えるのは、有機的な繋がりのある人間関係に囲まれていることは、幸福になるためにとても大事なことだということです。
そのために、ぜひ対話を大切にして欲しいのです。
対話をするのも簡単なことではありません。
時には勇気のいるときもあるかもしれません。
しかし、対話があるからこそ有機的な関係が深まり、互いに孤独から解放されるのだということを肝に銘じて努力して欲しいと思います。
良い職場もいい人間関係も、社員一人一人の努力と工夫の結晶なのです。